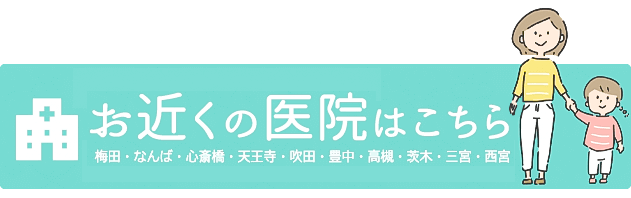矯正治療を受ける年齢は何歳ぐらいまでがいいの?
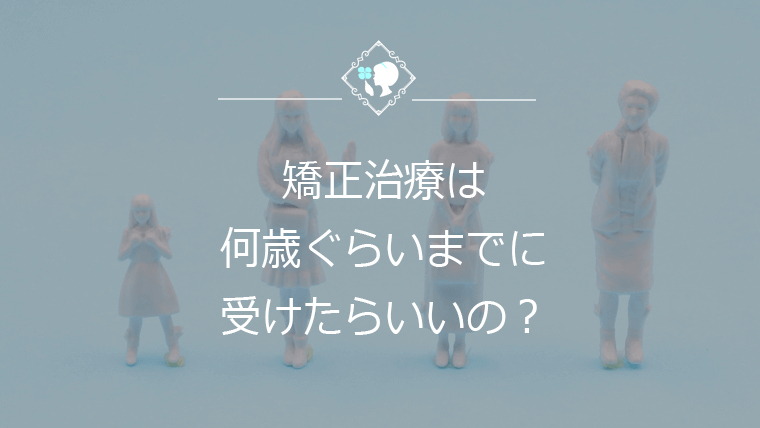
矯正治療を始める時期に関しては、歯科医師の間でも様々な意見があります。一般的には小児のうちに治療を行って後の大きさや形を適切に成長させると、将来出っ歯や受け口、ガタガタになる原因を排除することが可能です。大人の矯正では一般的には20歳くらいまでが歯が動きやすく、それ以降はやや歯が動きにくくなるため治療期間が長引く可能性があります。
目次
成長期に小児矯正を受けるメリット

成長期に小児矯正治療をすれば、子供の成長を利用しながら顎の発育を促進したり、逆に抑制することが出来ます。顎の大きさや形をコントロールすることによって、将来出っ歯や受け口、ガタガタの歯になるリスクを減らすことが出来ます。
受け口のお子さんには早期治療(3歳頃~)が絶対におすすめ

受け口は遺伝的要素が強いため、ご両親のどちらかが受け口の場合、お子さんも受け口になる可能性があります。
少しでもお子さんに受け口の兆候が見られたら、その時点で小児矯正の相談をされることをおすすめします。
早い時期に治療を開始すると、顎が過成長して受け口がひどくなる前に、顎の成長を抑えながら歯を並べていくことが出来ます。
受け口の場合は成長期を逃すと、成人してから治療をした場合、歯はきれいに並んでも、横顔を見ると顎が前に出た状態になっていることが多く、外科手術をして顎骨に直接アプローチしないと下顎を引っ込めることが出来ません。
受け口の治療は3~4歳から可能です。
顎が小さいお子さんには顎を成長させるための床矯正(5~6歳頃から)
顎が小さく、乳歯の状態で既に歯が並びきらないお子さんも、成長期であれば床矯正という方法で顎の横幅を広げるように成長を促すことが出来ます。床装置は取り外し可能で、プレート、拡大床などと呼ばれます。
骨格性の不正咬合の場合は子供の成長を利用して骨格の大きさや形を整えていくことで、将来不正咬合になるリスクを減らすことが出来ます。出っ歯や叢生の場合は、乳歯から永久歯に生え変わる5~6歳になったら治療を行うことが出来ます。
大人の矯正治療

大人になると、もう顎骨は成長しませんので、主に歯を動かして歯並びを整えていくことになります。大人の矯正で特に多いのは、抜歯によって歯が並ぶためのスペースを作ってから歯を動かしていく方法です。抜歯矯正と呼ばれます。
出っ歯や叢生の場合はその程度によって、抜歯が必要かどうかが決まります。八重歯の場合は、糸切り歯が大きく前に飛び出していることが多いため、抜歯してスペースを作らなければ、八重歯を正常な位置に戻すことが出来ません。
骨格性の出っ歯の場合は、歯を引っ込めただけでは口元が前に出た感じが改善しませんので、外科手術も視野に入れる必要があります。
受け口の場合は、骨格性のものが多いため、歯の向きを変えただけでは横顔がきれいになりません。しかしセットバック整形と呼ばれる外科手術をすればきれいになります。外科矯正は20歳以降に行うのが一般的です。
シニアの矯正患者さんもおられますが、歯周病になっている方は、先に歯周病の治療を受けて頂き、ある程度歯茎などの歯周組織の炎症がおさまって、健康な歯茎になってから矯正治療を開始します。
虫歯も同様に、矯正治療開始前に治療を終える必要があります。
矯正治療の時期についてのその他の要因

歯を動かすということだけを考えると、適した年齢は12歳から20歳位が良いといえます。この時期は顎骨の成長のピークを越えており、中高年の方と比べて骨が柔らかいため、歯が動きやすいです。
骨の成長のピークは、男子は12歳から13歳、女子は11歳頃といわれています。その後は男子で18歳~20歳ぐらいまで、女子で16歳~17歳くらいまでゆっくりと成長が継続すると考えられています。
また、受験期に歯列矯正が重なると、ストレスが大きくなる可能性があるため、受験期より前に治療を終えられるように、治療時期を考えるのも良いでしょう。
最近では大人の矯正は一般的になりましたし、30歳前後までは問題はありません。それ以降の年代では、個人差が大きくなりますが、若い方と比べると終了までの期間がやや長くなります。歯や骨に異常がなければ、年齢に関わらず歯列矯正は可能です。
2種類の矯正治療「歯列矯正」と「骨格矯正」
矯正治療は、歯列矯正と骨格矯正に分かれます。
歯列矯正は歯並びをきれいにするための矯正治療で、ガタガタを真っ直ぐに治したり、出っ歯を引っ込めたりするものです。
骨格矯正は顎の骨が原因で歯が出ていたり、顎の過成長が原因で受け口になっている場合に、場合によっては外科手術を行って顎骨の形を整えるという治療を行います。
矯正治療を受けるのに最適な時期に関するQ&A
矯正治療を始める最適な時期は何ですか?
最適な時期は患者さんの具体的な状況に依存しますが、一般的には12歳から20歳位が良いとされています。この時期は骨が柔らかく、歯の動きやすさがあります。
小児矯正治療のメリットは何ですか?
メリットには、顎の成長を利用して顎の大きさを歯が一列に並ぶのに適した大きさにできる点があります。
受け口のお子さんに早期治療がメリットがある理由は何ですか?
受け口のお子さんに早期治療がメリットがある理由は、成長期に顎の成長を促進または抑制できるからです。顎の成長が過成長する前に治療を始めることで、成人してからの顎の外科手術を避けることができます。
まとめ

歯列矯正の場合は、5~6歳くらいから矯正治療が可能です。受け口の子どものみ、3~4歳からの治療開始をおすすめします。大人になっても矯正は可能です。骨格が原因の出っ歯や受け口の方は、20歳以上になると外科手術も視野に入れる必要があります。
矯正治療を受けるのに最適な年齢については、多くの研究がありますが、一般的な合意はないようです。成人でも矯正治療を受けることは可能で、以下の研究がそれを示しています。
1. 成人における補助的矯正治療
50歳以上の成人においても、健康な歯周組織を有し、適切な残存歯を保持していれば、医学的に管理され、治療の推奨事項に従うことができれば、効果的な矯正治療が可能であるとされています。この研究では、補助的矯正治療を受けた50歳以上の患者が、最適な美的および機能的結果を得ることができたことが示されています。【Roberts, 1997】
2. 年齢に関する考慮事項
25歳から40歳の間の患者は、子供時代や思春期に矯正治療を受ける機会がなかった、またはその時期に治療の財政的な可能性がなかったためにきれいに整った歯列を望むことが多いです。40歳を超える成人は、移動歯や歯列不正などの自主的な理由、または複合的な口腔リハビリテーションのための歯周病専門医、補綴専門医、インプラント専門医の推奨により矯正治療を求めることがあります。【Decusară, Sincar, & Popa, 2018】
これらの研究から、矯正治療を受けるのに「最適」な年齢は特に定められておらず、多くの場合、個々の患者の状況によって異なることが分かります。歳を取っても、健康な歯周組織を持っているなら、治療を受けることが可能です。
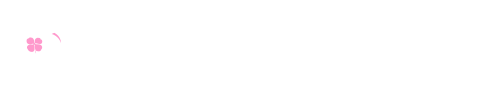
 医療法人真摯会
医療法人真摯会